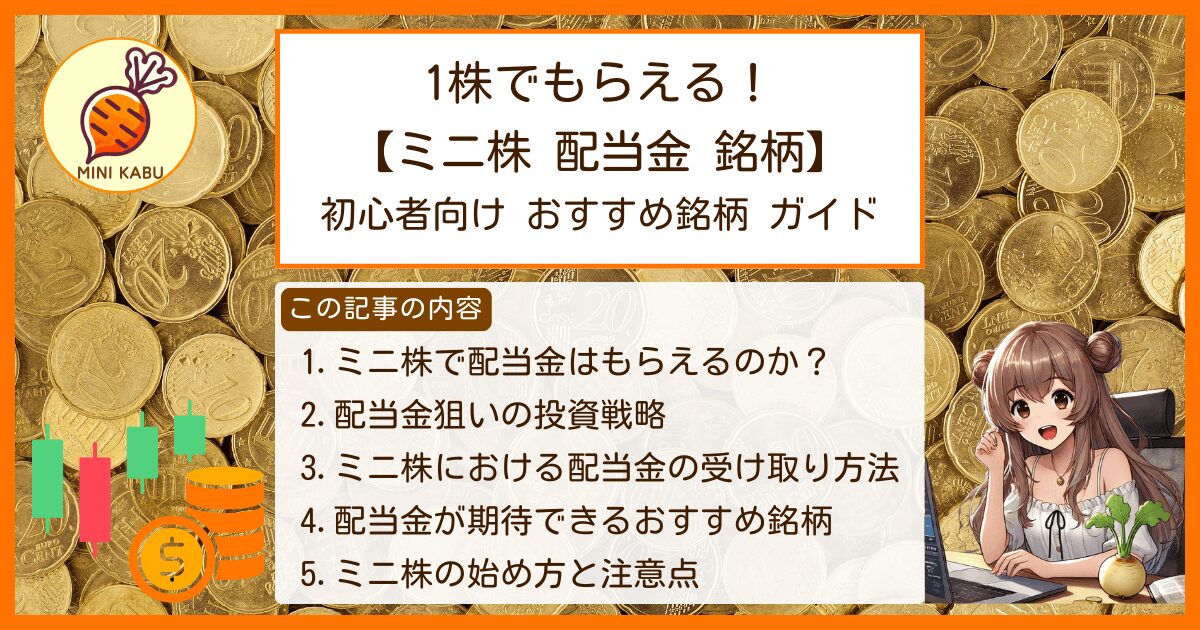1株で配当を受け取る
ミニ株(単元未満株)で少額から始める投資の魅力を知っていますか?
株式投資に興味があるけれど、「まとまった資金がない」「リスクを抑えたい」という理由で一歩踏み出せない方に、ミニ株はぴったりの選択肢です。
特に、高配当銘柄に投資することで、定期的な収入を得ながら資産形成が可能です。
このブログでは、配当金を狙ったミニ株投資のメリットや、証券会社ごとの特徴を詳しく解説しています。
少額投資から始めて、将来の資産を積み上げていく方法をぜひご覧ください。
SBI証券や楽天証券など、初心者でも安心して利用できる証券会社での口座開設の手順も説明しています。
今すぐ口座開設して、あなたも少額投資で配当金を手にしましょう!
ミニ株(単元未満株)の1番のメリットは、
数百円で株式投資の勉強ができること!
1.実際の市場での売買体験ができる
2.配当金・株主優待の体験ができる
3.投資判断力が鍛えられる
4.資産形成の基本が学べる
5.証券会社の使い方が身につく
本記事の注意事項(免責事項)
本記事は情報提供を目的としたものであり、特定の金融商品の勧誘を意図したものではありません。本記事に記載されている情報については、正確性、完全性、有用性を確保するために努力しておりますが、その保証は致しかねます。投資判断はご自身の責任で行ってください。本記事の内容を利用して生じたいかなる損害についても、当サイトおよび著者は一切の責任を負いかねます。詳しくは免責事項ページをご確認ください。
1. ミニ株(単元未満株)で配当金はもらえるのか?
実際に1株で「配当金」いただきました!
2024年12月
・日本製鉄株式会社(80円)
・テルモ(13円)
・三菱重工業株式会社(11円)
・日本電信電話株式会社(3円)
など
1.1 配当金の仕組み
ミニ株(単元未満株)でも通常の株式と同様に配当金を受け取ることが可能です。
企業が配当を行っている場合、保有している株数に応じて配当金が支払われます。
たとえば、1株につき50円の配当を行っている企業の株を10株保有していれば、500円の配当金を受け取ることができます。
ただし、単元未満株は議決権を持たないため、株主総会での投票権はありません。

ミニ株を使えば、少額からでも配当金を受け取れます。保有株数に応じた配当が、資産形成を助けてくれますよ。
1.2 配当金の計算方法と注意点
配当金の計算は、保有株数に対して1株あたりの配当額を掛けることで行われます。
ミニ株(単元未満株)でも、保有している株数に応じて配当金が支払われますが、少額投資の場合は受け取る配当金も少額になる点に注意が必要です。
また、配当金を受け取るためには、権利確定日(配当の権利を得るための最終売買日)までに株式を保有している必要があります。
さらに、配当金は税引き後の金額となるため、源泉徴収税などが差し引かれることも考慮しておく必要があります。

配当金は保有株数に応じて受け取れるから、少しずつ資産が増えますね。
1.3 議決権の有無について
ミニ株(単元未満株)を保有している株主には、通常の株主総会における議決権はありません。
これは、議決権が1単元(通常100株)に対して与えられるためです。
しかし、配当金や株主優待を受け取る権利は保持しているため、投資の目的としては十分にメリットがあります。
また、配当金を活用して資産を増やしていく戦略を取る投資家にとっては、議決権がないことは大きなデメリットではないでしょう。

ミニ株(単元未満株)には議決権がないけれど、配当金や株主優待は受け取れます。資産形成を目指すなら、議決権の有無はあまり気にしなくて大丈夫です。目的に合わせて賢く投資を続けましょう!
2. 配当金狙いの投資戦略
2.1 ミニ株(単元未満株)での長期保有戦略
株式投資を考えるとき、まずは長期的な視点が重要です。
特に、ミニ株(単元未満株)は少額から始められるため、初心者でも手軽に長期保有のメリットを享受することができます。
長期保有戦略では、株を長期間持ち続けることで、株価の上昇と配当金の両方を得る可能性が高まります。
配当金は、会社が利益を出した際に株主に還元されるもので、これを再投資することで、さらに大きなリターンを狙うことができます。

ミニ株なら、少額で長期保有のメリットを享受できます。
(1)ミニ株(単元未満株)での配当金の魅力
ミニ株(単元未満株)でも通常の株と同じく、保有している株に応じて配当金を受け取ることができます。
配当金は少額かもしれませんが、積み重ねることでかなりの額になる可能性があります。
例えば、SBI証券の「S株」では、ミニ株(単元未満株)の保有でもしっかりと配当金が得られます。
また、楽天証券の「かぶミニ」やマネックス証券の「ワン株」、auカブコム証券の「プチ株」でも同様に、ミニ株(単元未満株)でも配当を受け取ることが可能です。
長期保有戦略では、これらの配当金を再投資することで「複利の力」を活かすことができます。
つまり、配当金でさらに株を買い増し、それに対してまた配当が得られるという循環が生まれます。
たとえ最初は少額でも、長期間続けることで大きな資産形成が可能になります。

ミニ株を活用すれば、少額からでも配当金を受け取れます。長期保有で再投資し、複利の力を活かして資産を育てていきましょう。
(2)成長株と安定株のバランスを意識
ミニ株(単元未満株)を使って長期保有する際、株式の選び方も重要です。
成長が期待できる企業の株式は、将来的に株価が大幅に上昇する可能性があります。
一方で、安定した収益を出し続けている企業の株式は、安定した配当を期待できます。
SBI証券の「S株」や楽天証券の「かぶミニ」、マネックス証券の「ワン株」、auカブコム証券の「プチ株」では、多様な銘柄を少額から購入できるので、自分に合ったバランスを見つけることができます。

ミニ株を活用して成長株と安定株をうまく組み合わせよう。リスクを抑えつつ、将来のリターンを狙えるバランスが大事です。
2.2 分散投資とリスク管理
株式投資において「分散投資」と「リスク管理」は成功への鍵と言っても過言ではありません。
特にミニ株(単元未満株)を活用すれば、少額からでも効率的に分散投資ができるため、リスクを軽減しながら投資を進めることが可能です。
株式投資初心者にとっては、リスクを取らずに収益を上げることが最優先と感じがちですが、実際には適切なリスク管理を行うことで、投資の安定性と成功率が大幅に向上します。
(1)分散投資とは?
分散投資とは、単一の銘柄や業種に偏らず、複数の異なる銘柄や業種に資金を分散して投資することを指します。
なぜこれが重要かというと、もし一つの銘柄に全額投資していた場合、その銘柄の株価が下がると投資資金全体が大きく減少するリスクがあるからです。
逆に、複数の銘柄に分散投資しておけば、ある銘柄が下がっても他の銘柄がカバーしてくれることがあり、リスクを分散できるのです。
例えば、SBI証券の「S株」や楽天証券の「かぶミニ」、マネックス証券の「ワン株」、auカブコム証券の「プチ株」では、少額からさまざまな銘柄を購入できるため、初めての投資でも無理なく分散投資を行うことができます。

分散投資は、リスクを抑えながら資産を守るための重要な戦略です。少額からでも、いろんな銘柄に投資することで安心感が増します。
(2)リスク管理の重要性
リスク管理とは、予想外の損失を最小限に抑えるための手法です。
株式市場は常に変動しており、短期的には株価が大きく動くことがあります。
初心者でも、適切なリスク管理を行えば、こうした変動に対するストレスを減らし、安定した投資ライフを送ることができます。
例えば、ミニ株(単元未満株)のメリットは、少額から始められる点にあります。
SBI証券の「S株」を利用すれば、1株単位での購入が可能です。
これにより、手持ちの資金を数社に分散させることができ、投資リスクを分散できます。
楽天証券の「かぶミニ」やauカブコム証券の「プチ株」も同様に、少額から多様な銘柄に投資できるため、初めての投資家にとっても安心です。

リスク管理は、安定した投資生活に欠かせないものです。少額からミニ株を活用して、分散投資を始めてみてくださいね。
(3)分散投資を実践する方法
分散投資を行う際には、業種や国、企業規模などさまざまな観点から銘柄を選ぶことがポイントです。
例えば、一つの業種が不調でも、他の業種が好調であれば、全体の損失を抑えることができます。
さらに、海外株式や異なる通貨での投資を組み合わせることで、より幅広いリスク分散が可能です。
マネックス証券の「ワン株」では、日本株だけでなく、米国株にも投資できるため、国内外の銘柄を組み合わせた分散投資が可能です。
これにより、異なる経済状況に対応した投資戦略を取ることができ、リスク管理の幅を広げることができます。

業種や国を分散させて投資することで、リスクを軽減できます。少額から始められるミニ株を使って、安心して分散投資を実践してみてください。
2.3 配当金再投資のメリット
配当金再投資とは、企業から受け取った配当金をそのまま使うのではなく、再び株式の購入に充てることを指します。
この再投資によって得られる大きなメリットは「複利の力」です。
株式投資初心者でも、この「複利」の概念を理解し実践することで、資産を着実に増やすことが可能です。
(1)複利の力を活かす配当金再投資
「複利」とは、得られた利益をさらに投資に回し、利益が利益を生む仕組みです。
たとえば、株式の配当金を使って追加の株を購入すると、その購入した株にも今後配当金が発生します。
この循環を続けることで、資産は雪だるま式に増えていくのです。
たとえ配当金が少額でも、長期間にわたって配当金を再投資していくことで、最初の元本が徐々に大きくなり、その結果、受け取る配当金も増えていきます。
この「時間」と「再投資」のコンビネーションが、最終的には大きな利益を生む可能性があるのです。
例えば、SBI証券の「S株」を利用して少額ずつ株を購入し、そこから得られた配当金を再投資することで、手持ちの株数を増やしながら、長期的な利益を目指すことができます。
同様に、楽天証券の「かぶミニ」やマネックス証券の「ワン株」、auカブコム証券の「プチ株」でも配当金再投資を行い、効率的に資産を増やすことが可能です。

配当金を再投資することで、複利の効果を最大限に活かせます。少額からでも、長期間続けることで資産が増えていくのを実感できますよ。
(2)配当金再投資の例:10年後の資産はどうなる?
配当金再投資の効果を具体的に見てみましょう。
仮に、年間3%の配当利回りを持つ株を購入し、その配当金を毎年再投資した場合、10年後には最初の投資額に対してどれくらいの資産増加が期待できるでしょうか。
例えば、10万円の投資を行い、毎年3%の配当金が再投資されると、10年後には複利効果によっておよそ13万円以上に増える計算となります。
これが配当金を再投資しなかった場合、10年間で受け取る配当は単純に3万円となり、再投資による増加分がいかに大きいかがわかります。
このように、配当金再投資は、株式投資の成功を後押しする重要な戦略です。

配当金再投資で、資産が大きく育ちますよ!
(3)ミニ株での配当金再投資のメリット
ミニ株(単元未満株)を利用すれば、少額からでも配当金再投資が可能です。
SBI証券の「S株」では1株単位での購入が可能ですし、楽天証券の「かぶミニ」やマネックス証券の「ワン株」、auカブコム証券の「プチ株」でも同様に少額から株を購入し、配当金を再投資することができます。
初心者が始めやすい環境が整っているミニ株で配当金再投資を行うことで、長期的な資産形成を無理なく進めることが可能です。
特に、長期保有を考える場合、この再投資の効果を最大限に活かすことが、成功への鍵となります。

ミニ株を使えば、少額から配当金再投資が可能です。これにより、無理なく長期的な資産形成を進められます。投資の第一歩を踏み出しましょう!
3. ミニ株(単元未満株)における配当金の受け取り方法
SBI証券、楽天証券、マネックス証券、auカブコム証券では、それぞれミニ株(単元未満株)における配当金受け取り方法に若干の違いがあります。
3.1 証券会社による違い
ミニ株(単元未満株)を購入する際、証券会社ごとに提供しているサービスや手数料、取引方法に違いがあります。
これらの違いを理解することは、初心者が賢く投資を始めるための重要なポイントです。
各証券会社の特徴を知ることで、自分に合った最適な証券会社を選び、効率的な投資を進めることができます。
(1)SBI証券の「S株」
SBI証券は、株式投資をする多くの投資家に支持されている大手証券会社の一つです。
「S株」と呼ばれる単元未満株の取引が特徴で、1株単位での購入が可能です。
これにより、投資資金が少ない場合でも、気になる企業の株を購入することができます。
SBI証券の「S株」の大きな特徴は、手数料の安さです。
特に、少額の取引を行う際にかかるコストが低く抑えられているため、ミニ株を長期的に保有したいと考える初心者にとっては魅力的な選択肢となります。
また、配当金を受け取ることもできるので、再投資を通じて資産を着実に増やしていくことが可能です。
詳しくは、 SBI証券の公式サイト をご覧ください。

SBI証券の『S株』は、少額から1株単位での投資が可能です。手数料も安く、配当金の再投資で資産を増やせます。初心者にぴったりです!
(2)楽天証券の「かぶミニ」
楽天証券は、豊富な商品ラインアップや便利な取引ツールが人気の証券会社です。
「かぶミニ」と呼ばれる単元未満株の取引サービスを提供しており、こちらも1株単位での購入が可能です。
楽天証券の大きなメリットは、楽天ポイントを使って株を購入できる点です。
これにより、普段のショッピングなどで貯まったポイントを投資に活用することができ、初心者にとって非常に手軽な投資方法となります。
また、楽天証券の「かぶミニ」では、手数料も比較的低く設定されているため、少額からスタートしたい方にとって非常にコストパフォーマンスが高い選択肢となります。
詳しくは、 楽天証券の公式サイト をご覧ください。

楽天証券の『かぶミニ』は、1株から購入できて、楽天ポイントも使えるから、投資がとても手軽になります。少額からスタートしやすいですよ!
(3)マネックス証券の「ワン株」
マネックス証券もミニ株投資をする初心者におすすめの証券会社です。
「ワン株」と呼ばれるサービスを提供しており、これもまた1株単位での取引が可能です。
特に、米国株を含めた国際的な投資にも対応しているため、国内外の株式に幅広く投資をしたいと考える方には非常に魅力的です。
「ワン株」では、手数料がやや割高に感じられる場合がありますが、長期的な投資を行い配当金を再投資することで、このコストを十分にカバーできます。
また、マネックス証券のツールは初心者にも使いやすく、投資を始めたばかりの方でも簡単に取引を行うことができるのが強みです。
詳しくは、 マネックス証券の公式サイト をご覧ください。

マネックス証券の『ワン株』は、1株から取引できる便利なサービス。国内外の株に手軽に投資でき、初心者でも使いやすいツールが揃っています。
(4)auカブコム証券の「プチ株」
auカブコム証券は、KDDIグループの一員として信頼性が高く、多くの投資家に支持されています。
「プチ株」と呼ばれるサービスを通じて単元未満株の取引が可能で、少額から株式投資を始めることができます。「プチ株」の大きな特徴は、積立投資に対応している点です。
これにより、定期的に少額ずつ株を購入することができ、初心者でも無理なく長期的な投資を続けることができます。
また、auカブコム証券の「プチ株」では、他の証券会社と同様に配当金を受け取ることができ、その配当金を再投資することで資産を増やすことができます。
詳しくは、 auカブコム証券の公式サイト ご覧ください。

auカブコム証券の『プチ株』は、少額からの投資と積立が可能です。初心者でも手軽に長期的な資産形成ができるので、とても安心です!
■主な証券会社のミニ株(単元未満株)比較
| 項目 | SBI証券 | 楽天証券 | マネックス証券 | 三菱UFJ eスマート証券 |
|---|---|---|---|---|
| ミニ株名 | S株 | かぶミニ | ワン株 | プチ株 |
| 買付手数料 | 無料 | 無料 | 無料 | 0.55%(最低52円) |
| 売却手数料 | 無料 | 無料 | 0.55%(最低52円) | 0.55%(最低52円) |
| 往復コスト 参考価格:6千円 | 0円 | 27円 | 52円 | 104円 |
| スプレッド | なし | リアルタイム取引 0.22% 寄付取引 無料 | なし | なし |
| 取引時間 | 受付は24時間 市場への発注は1日3度 ■前営業日14:00~当日7:00 前場始値向けの注文 ■当日7:00~10:30 後場始値向けの注文 ■当日10:30~14:00 当日後場引け(終値)向けの注文 | 受付時間 リアルタイム取引 取引時間と同じ 寄付取引 17:00~翌8:45 ■リアルタイム取引 9:00~11:30 12:30~15:25 ■寄付取引 前場 寄付 | 受付時間 17:30頃~翌11:30 ■1日1回の約定 当日午前11時30分までの注文が原則として後場の始値で約定 約定結果は16時10分頃に反映 | 受付は24時間 ■00:01~10:00 当日後場始値 ■10:01~23:00 翌営業日前場始値 ■23:01~24:00 翌営業日後場始値 ■休日(土・日・祝祭日) 翌営業日後場始値 |
| リアルタイム取引 | × | ○ | × | × |
| 成行注文 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 指値注文 | × | ○ | × | × |
| 積立投資 | × | ○ | × | ○ |
| 貸株サービス | × | × | ○ | × |
| ポイント 投資 | × | ○(楽天ポイント) | × | ○(Pontaポイント) |
| NISA口座 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 項目 | SBI証券 | 楽天証券 | マネックス証券 | 三菱UFJ eスマート証券 |
|---|---|---|---|---|
| ミニ株名 | S株 | かぶミニ | ワン株 | プチ株 |
| 買付手数料 | 無料 | 無料 | 無料 | 0.55%(最低52円) |
| 売却手数料 | 無料 | 無料 | 0.55%(最低52円) | 0.55%(最低52円) |
| 往復コスト 参考価格:6千円 | 0円 | 27円 | 52円 | 104円 |
| スプレッド | なし | リアルタイム取引 0.22% 寄付取引 無料 | なし | なし |
| 取引時間 | 受付は24時間 市場への発注は1日3度 ■前営業日14:00~当日7:00 前場始値向けの注文 ■当日7:00~10:30 後場始値向けの注文 ■当日10:30~14:00 当日後場引け(終値)向けの注文 | 受付時間 リアルタイム取引 取引時間と同じ 寄付取引 17:00~翌8:45 ■リアルタイム取引 9:00~11:30 12:30~15:25 ■寄付取引 前場 寄付 | 受付時間 17:30頃~翌11:30 ■1日1回の約定 当日午前11時30分までの注文が原則として後場の始値で約定 約定結果は16時10分頃に反映 | 受付は24時間 ■00:01~10:00 当日後場始値 ■10:01~23:00 翌営業日前場始値 ■23:01~24:00 翌営業日後場始値 ■休日(土・日・祝祭日) 翌営業日後場始値 |
| リアルタイム取引 | × | ○ | × | × |
| 成行注文 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 指値注文 | × | ○ | × | × |
| 積立投資 | × | ○ | × | ○ |
| 貸株サービス | × | × | ○ | × |
| ポイント 投資 | × | ○(楽天ポイント) | × | ○(Pontaポイント) |
| NISA口座 | ○ | ○ | ○ | ○ |
※2024年10月05日現在
3.2 配当金受領の手続き
配当金は、株を保有している株主に対して企業が利益の一部を還元するもので、株式投資において非常に魅力的なポイントです。
しかし、初心者にとって「配当金の受領手続き」と聞くと少し複雑に感じるかもしれません。
ここでは、各証券会社での配当金の受領方法や注意点を詳しく解説し、スムーズに配当金を受け取るための流れを紹介します。
(1)配当金受領方法の基本
まず、株を保有していると、企業が配当金を支払うタイミングで配当を受け取ることができます。
配当金の受領方法は大きく分けて以下の3つがあります。
- 銀行振込による受取
配当金を指定した銀行口座に直接振り込んでもらう方法です。
事前に証券会社で銀行口座を登録しておくことで、配当金が振り込まれるため、受取手続きが簡単です。
ほとんどの証券会社でこの方法を利用できます。 - ゆうちょ銀行での受取
配当金をゆうちょ銀行で受け取る方法です。
配当金が支払われる際に、証券会社から「配当金通知書」が郵送されてきます。
この通知書を持参して、郵便局またはゆうちょ銀行で配当金を現金で受け取ることができます。
この方法は、特に銀行口座を指定したくない場合に便利です。 - 株式数比例配分方式
こちらは、証券会社の口座に直接配当金が入る方法です。
特に、SBI証券や楽天証券、マネックス証券、auカブコム証券など、多くの証券会社が対応しており、株を保有している証券口座にそのまま配当金が入金されるため、非常にシンプルで管理もしやすいです。
株式投資初心者にはこの方法が最もおすすめです。

配当金を受け取る方法は簡単です。銀行振込やゆうちょ銀行での受取、証券口座への直接入金など、選択肢が豊富です。特に、証券口座に直接入金される方法は初心者におすすめ。これで安心して株式投資を続けられますよ。
(2)SBI証券の「S株」での配当金受取
SBI証券では、配当金の受領方法として「株式数比例配分方式」が利用できます。
これにより、配当金は自動的にSBI証券の口座に入金されます。
銀行口座への振込設定や、ゆうちょ銀行での受取も可能ですので、自分に合った方法を選ぶことができます。
詳細な手続きについては、 SBI証券の公式サイト をご覧ください。
(3)楽天証券の「かぶミニ」での配当金受取
楽天証券の「かぶミニ」でも、配当金の受領方法は株式数比例配分方式が基本となっています。
楽天証券の口座に自動的に配当金が入金されるため、特別な手続きをする必要がなく、初心者にとって非常に便利です。
また、楽天ポイントと組み合わせた投資も可能なので、配当金を利用したさらなる資産形成が期待できます。
詳しくは、 楽天証券の公式サイト をご覧ください。
(4)マネックス証券の「ワン株」での配当金受取
マネックス証券の「ワン株」でも、株式数比例配分方式を利用して、配当金を自動的に証券口座で受け取ることができます。
手続きも簡単で、口座内で配当金を管理することで、再投資もスムーズに行えます。
銀行振込や郵便局での受取も対応しているため、柔軟な選択が可能です。
詳しくは、 マネックス証券の公式サイト をご覧ください。
(5)auカブコム証券の「プチ株」での配当金受取
auカブコム証券の「プチ株」でも、配当金は株式数比例配分方式で受け取ることができます。
証券口座に直接配当金が入金されるため、手続きも簡単で管理が楽です。
また、積立投資との組み合わせで、長期的な資産形成がしやすくなっています。
銀行振込や郵便局での現金受取にも対応しているため、好みに合わせた方法を選べます。
詳しくは、 auカブコム証券の公式サイト ご覧ください。
(6)配当金受領時の注意点
配当金を受け取る際には、配当の支払日や、証券会社による手数料の有無を確認しておくことが重要です。
また、配当金が発生するタイミング(配当基準日)に株を保有している必要があるため、取引スケジュールも把握しておくと良いでしょう。
証券会社ごとに異なる条件がある場合もあるため、事前に確認しておくことでスムーズに配当金を受け取ることができます。

配当金を受け取るときは、支払日や手数料を確認しておくと安心です。取引スケジュールも忘れずにチェックしてね。
4. 配当金が期待できるおすすめ銘柄
4.1 高配当銘柄の探し方
株式投資において、「高配当銘柄」は非常に魅力的な選択肢です。
高配当銘柄とは、配当利回りが高い企業の株式を指し、これらの銘柄を保有することで安定的に配当金を得ることができます。
しかし、初心者にとって「どうやって高配当銘柄を探せばよいか?」は少し難しく感じるかもしれません。
ここでは、株式投資初心者でも簡単に高配当銘柄を見つける方法を詳しく解説します。
(1)高配当銘柄とは?
まず、「配当利回り」という用語を理解しましょう。
配当利回りとは、企業が支払う年間の配当金を株価で割ったもので、投資した資金に対してどれだけの配当が得られるかを示します。
例えば、株価が1,000円で年間配当金が50円の場合、配当利回りは5%です。
一般的に配当利回りが3%以上の銘柄は「高配当銘柄」と呼ばれ、配当金を重視する投資家に人気があります。
高配当銘柄を選ぶ際には、単に配当利回りが高いだけでなく、企業の業績や将来性、配当金の安定性にも注目することが重要です。

高配当銘柄は、配当利回りだけでなく、企業の安定性も考えて選ぼう!
(2)SBI証券の「S株」を使った高配当銘柄の探し方
SBI証券の「S株」は、少額から投資できる単元未満株のサービスです。
このサービスを活用すれば、高配当銘柄に少額から分散投資することができます。
SBI証券のサイトには、「高配当銘柄ランキング」や「配当利回り検索機能」があり、これを使って簡単に高配当銘柄を探すことができます。
また、SBI証券の「銘柄スクリーニング」ツールを使うと、配当利回りや企業の財務状況、業績などの条件で銘柄を絞り込むことができるため、初心者でも自分に合った高配当銘柄を見つけることが可能です。
さらに詳しい方法については、 SBI証券の公式サイト をご覧ください。

SBI証券の『S株』を使えば、少額から高配当銘柄に分散投資できます。便利な検索機能を活用して、自分にぴったりの銘柄を見つけてみてくださいね。
(3)楽天証券の「かぶミニ」で高配当銘柄を見つける方法
楽天証券の「かぶミニ」でも、少額から高配当銘柄に投資が可能です。
楽天証券の強みは、投資信託やETFも充実しているため、高配当株式に加えて、安定的に配当を得られる商品を選ぶことができます。
また、楽天ポイントを利用して株を購入できるため、ポイントを活用してリスクを抑えながら高配当銘柄に投資することができます。
楽天証券の「銘柄スクリーニング」ツールでは、配当利回りやPER(株価収益率)などの指標を元に、高配当銘柄を簡単に見つけることができるため、初心者でも使いやすいです。
詳細な使い方については、楽天証券の公式サイト をご覧ください。

楽天証券の『かぶミニ』を使えば、少額から高配当銘柄に投資可能です。ポイントも活用してリスクを抑えながら、安定した配当を目指しましょう。
(4)マネックス証券の「ワン株」を使った高配当銘柄の探し方
マネックス証券の「ワン株」でも、高配当銘柄を少額で購入することができます。
マネックス証券の特徴は、国内株だけでなく米国株にも対応している点です。
米国株には、日本企業と比べて高配当銘柄が多く、特に配当を重視する投資家には魅力的です。
マネックス証券の「銘柄スカウター」や「米国株の高配当ランキング」などのツールを活用すれば、配当利回りや業績を基準に銘柄を探すことができます。
国内外の銘柄を比較して、より多くの選択肢から高配当銘柄を選ぶことができるのは、マネックス証券の大きな強みです。
さらに詳細は、マネックス証券の公式サイト をご覧ください。

マネックス証券の『ワン株』を利用すれば、少額から国内外の高配当銘柄に投資できます。ツールを活用して、自分にぴったりの銘柄を見つけてみましょう!
(5)auカブコム証券の「プチ株」での高配当銘柄の選び方
auカブコム証券の「プチ株」は、少額で高配当銘柄に分散投資ができる便利なサービスです。
「プチ株」では、積立投資が可能であり、高配当銘柄に定期的に投資を続けることで、配当金を受け取りつつ、資産を増やしていくことができます。
auカブコム証券のサイトでも、高配当銘柄を探すためのスクリーニング機能が充実しており、投資の際には手軽に使えるツールが揃っています。
配当利回りの高い銘柄を定期的に積立投資することで、長期的に安定した収入源を作ることが可能です。
詳細については、auカブコム証券の公式サイト ご覧ください。

auカブコム証券の『プチ株』なら、少額から高配当銘柄への分散投資が可能です。定期的に積立てて、安定した収入源を目指しましょう!
4.2 配当利回りが高い銘柄例
具体的な高配当銘柄としては、以下のような銘柄があります。
これらの銘柄は、配当利回りが高く、株主への還元が期待できる企業です。
(1)ソフトバンク
(2)日本たばこ産業(JT)
(3)商船三井
(4)日本郵船
(5)三井住友フィナンシャルグループ
(6)住友商事
(7)りそなホールディングス
(8)ENEOSホールディングス
(9)オリックス
(10)SOMPOホールディングス
※最新情報は各企業の公式発表をご確認ください。

ここでは、1株から購入でき、高配当が期待できる銘柄を、根拠や特徴とともに詳しく紹介します。
(1)ソフトバンク
| 👍株価 | 215.4円 / 1株 | 2025年3月6日 |
| 👍配当金 | 8.6円 / 1株 | 2024年3月 実績 |
| 👍配当利回り | 約 4.0 % | (予想) |
| 👍株価 | 215.4円 / 1株 | 2025年3月6日 |
| 👍配当金 | 8.6円 / 1株 | 2024年3月実績 |
| 👍配当利回り | 約 4.0 % | (予想) |

携帯やPayPayで有名なソフトバンクだね!
<詳細情報>
| 証券コード | 9434 |
| 企業概要 | ソフトバンクグループの中核を担う通信事業会社。 携帯通信(SoftBank/Y!mobile/LINEMO)、固定通信、ブロードバンドなどの通信基盤上に、Yahoo! JAPANやPayPayなどのITサービスを提供しています。 移動通信とICTソリューションを融合し、法人向けにもクラウドやIoTサービスを展開する総合通信企業です。 |
| 将来性 | 安定した通信収入を基盤に、今後は5G/6GやIoT分野での成長が期待されます。 |
| リスク要因 | 携帯料金引き下げ圧力や楽天など新規参入による顧客流出リスクがあります。 |
| 特徴 | インフラ株ならではのディフェンシブ性と高配当が特徴です。 |
| 根拠 | 株価1万円以下どころか数百円台で購入でき(※株式分割の恩恵)、なおかつ利回り4%超の高配当である点を評価しました。 |
| 株価 | 215.4円 / 1株(2025/03/06) |
| 1株あたり配当金 | 8.6円(2024年3月 実績) |
| 配当利回り | 約4.0%(予想) |
| 詳細 | <https://www.softbank.jp/corp/> |
(2)日本たばこ産業(JT)
| 👍株価 | 3,858円 / 1株 | 2025年3月6日 |
| 👍配当金 | 194円 / 1株 | 2024年12月 実績 |
| 👍配当利回り | 約 5.2 % | (予想) |
| 👍株価 | 3,858円 / 1株 | 2025年3月6日 |
| 👍配当金 | 194円 / 1株 | 2024年12月実績 |
| 👍配当利回り | 約 5.2 % | (予想) |

タバコのJTって、飲み物も出してるよね。
<詳細情報>
| 証券コード | 2914 |
| 企業概要 | 日本国内のたばこ製造を独占するたばこメーカー。 メビウス(旧マイルドセブン)など紙巻たばこの国内トップブランドを持ち、海外M&Aで買収したキャメルなどの海外たばこ事業も展開しています。 。加熱式たばこ「プルーム」シリーズにも注力中。その他、医薬品や加工食品(テーブルマークの冷凍食品等)も手掛ける多角化企業です。 |
| 将来性 | 5G紙巻きたばこ市場は年々縮小していますが、JTは海外展開で販売数量を補完し収益を維持しています。 |
| リスク要因 | 喫煙率低下や各国のたばこ規制強化が根本的なリスクです。 |
| 特徴 | 通信インフラを支え安定高配当の代表格であり、「配当金生活」志向の投資家にも人気です。 |
| 根拠 | 利回り約5%超という突出した配当利回りが最大の選定理由です。 |
| 株価 | 3,858円 / 1株(2025/03/06) |
| 1株あたり配当金 | 194円(2024年12月 実績) |
| 配当利回り | 約5.2%(予想) |
| 詳細 | <https://www.jti.co.jp/> |
(3)商船三井
| 👍株価 | 5,606円 / 1株 | 2025年3月6日 |
| 👍配当金 | 220円 / 1株 | 2024年3月実績 |
| 👍配当利回り | 約 6.1 % | (予想) |
| 👍株価 | 5,606円 / 1株 | 2025年3月6日 |
| 👍配当金 | 220円 / 1株 | 2024年3月実績 |
| 👍配当利回り | 約 6.1 % | (予想) |

船で荷物運ぶ商船三井って有名だよね!
<詳細情報>
| 証券コード | 9104 |
| 企業概要 | 日本を代表する海運会社の一つで、鉄鉱石や石油を運ぶ大型ばら積み船やタンカー、LNG船など世界最大級の船隊を擁します。 定期コンテナ航路や不定期専用船、フェリーなど海運全般を手掛ける総合海運企業です。 川崎汽船・日本郵船と並ぶ国内海運“三大メガキャリア”の一角で、東南アジアなどグローバル展開もしています。 |
| 将来性 | 海運市況は変動が大きいものの、直近は好調でした。商船三井は2023年度に史上最高益を更新し、配当金の大幅増額も発表。 |
| リスク要因 | 景気変動による海運市況の乱高下が最大リスクです。 |
| 特徴 | 海運株は景気連動型ですが、その分配当利回りが際立って高い点が特徴です。 |
| 根拠 | 収益性が高く、配当性向も健全で、長期的に安定利回り6%前後という群を抜く高さに注目しました。 |
| 株価 | 5,606円(2025/03/06) |
| 1株あたり配当金 | 220円(2024年3月 実績) |
| 配当利回り | 約6.1%(予想) |
| 詳細 | <https://www.mol.co.jp/> |
(4)日本郵船
| 👍株価 | 5,333円 / 1株 | 2025年3月6日 |
| 👍配当金 | 140円 / 1株 | 2024年3月実績 |
| 👍配当利回り | 約 5.9 % | (予想) |
| 👍株価 | 5,333円 / 1株 | 2025年3月6日 |
| 👍配当金 | 140円 / 1株 | 2024年3月実績 |
| 👍配当利回り | 約 5.9 % | (予想) |

郵便じゃなくて海運会社、日本郵船だよ。
<詳細情報>
| 証券コード | 9101 |
| 企業概要 | 総合海運大手で、売上高では国内トップ規模を誇ります。 コンテナ船から自動車船、ドライバルク船、LNG船、航空貨物(ANAとの共同出資)まで、海・陸・空を組み合わせた総合物流サービスを展開しています。 三菱商事系列で、商船三井・川崎汽船と連合でコンテナ事業会社ONEを運営しています。 |
| 将来性 | 世界的な物流需要の増減に左右されますが、NYKも近年のコンテナ市況高騰で巨額の利益を計上しました。 |
| リスク要因 | 商船三井同様、海運市況変動リスクが大きいです。 |
| 特徴 | 日本最大のエネルギー郵船は総合海運トップとして規模が大きく、安定性が比較的高いです。 |
| 根拠 | 直近の高配当(利回り5~6%)と、総合物流企業としての安定感が根拠です。 |
| 株価 | 5,333円(2025/03/06) |
| 1株あたり配当金 | 140円(2024年3月 実績) |
| 配当利回り | 約5.9%(予想) |
| 詳細 | <https://www.nyk.com/> |
(5)三井住友フィナンシャルグループ
| 👍株価 | 3,838円 / 1株 | 2025年3月6日 |
| 👍配当金 | 90円 / 1株 | 2024年3月実績 |
| 👍配当利回り | 約 3.2 % | (予想) |
| 👍株価 | 3,838円 / 1株 | 2025年3月6日 |
| 👍配当金 | 90円 / 1株 | 2024年3月実績 |
| 👍配当利回り | 約 3.2 % | (予想) |

三井住友って、銀行でよく聞く名前だね。
<詳細情報>
| 証券コード | 8316 |
| 企業概要 | 日本を代三井住友銀行(SMBC)を中核に、SMBC日興証券、SMBC信託銀行、三井住友カードなどを傘下に持つメガバンク持株会社。 都市銀行として法人・個人向け銀行業務全般を展開し、収益力はメガバンク中でもトップ級と評価されています。 海外にも広く進出し、アジアを中心にグローバル銀行展開しています。 |
| 将来性 | 金融行政の緩和などもありメガバンクは収益改善傾向です。 |
| リスク要因 | 国内低金利環境が続くと利ざや縮小で銀行収益が伸び悩むリスクがあります。 |
| 特徴 | メガバンク株の中で最も利回りが高めであり、PBRも1倍以下と割安です。 |
| 根拠 | 株価が比較的安定株価1万円以下で安心感のある高配当として選びました。 |
| 株価 | 3,838円(2025/03/06) |
| 1株あたり配当金 | 90円(2024年3月 実績) |
| 配当利回り | 約3.2%(予想) |
| 詳細 | <https://www.smfg.co.jp/> |
(6)住友商事
| 👍株価 | 3,470円 / 1株 | 2025年3月6日 |
| 👍配当金 | 125円 / 1株 | 2024年3月実績 |
| 👍配当利回り | 約 4.5 % | (予想) |
| 👍株価 | 3,470円 / 1株 | 2025年3月6日 |
| 👍配当金 | 125円 / 1株 | 2024年3月実績 |
| 👍配当利回り | 約 4.5 % | (予想) |

いろんな事業やってる総合商社の住友商事だよね。
<詳細情報>
| 証券コード | 8053 |
| 企業概要 | 総合商社大手で、金属、エネルギー、機械、化学品、食品、金融、不動産など多岐にわたる事業投資を行う複合企業。 住友グループの一角で、国内外に強力な事業基盤を持ちます。特に金属資源(鉱山権益)やインフラ(発電・交通)に強みがあり、新興国での大型プロジェクトにも参画しています。 |
| 将来性 | 資源高局面では大きな利益を計上し、近年は商社全般で業績が好調でした。 |
| リスク要因 | 原油価格資源価格や為替の変動が収益に大きく影響します。 |
| 特徴 | 総合商社株は高配当と事業分散による安定感が魅力です。 |
| 根拠 | 利回り4%超の高配当かつ事業ポートフォリオが多角的な点を評価しました。 |
| 株価 | 3,470円(2025/03/06) |
| 1株あたり配当金 | 125円(2024年3月 実績) |
| 配当利回り | 約4.5%(予想) |
| 詳細 | <https://www.sumitomocorp.com/ja/jp/> |
(7)りそなホールディングス
| 👍株価 | 1,248円 / 1株 | 2025年3月6 |
| 👍配当金 | 22円 / 1株 | 2024年3月実績 |
| 👍配当利回り | 約 4.0 % | (予想) |
| 👍株価 | 1,248円 / 1株 | 2025年3月6 |
| 👍配当金 | 22円 / 1株 | 2024年3月実績 |
| 👍配当利回り | 約 4.0 % | (予想) |

銀行のりそな、緑色のロゴが目印だな。
<詳細情報>
| 証券コード | 8308 |
| 企業概要 | 旧大和銀行とあさひ銀行の統合で発足した都市型地方銀行グループです。 傘下にりそな銀行(都市銀)、埼玉りそな銀行、関西みらい銀行など地方銀行3行を持ち、首都圏と近畿圏を地盤とします。 中小企業融資や個人向けリテール業務に強みがあり、地銀としては珍しく全国区の展開をしています。 |
| 将来性 | メガバンクに次ぐ規模の金融グループとして、地域密着と都市銀行機能を両立させています。 |
| リスク要因 | 地域景況悪化による融資焦げ付きリスクや、不動産融資問題などによる信用コスト増大リスクがあります。 |
| 特徴 | 地銀株の中では異色の全国銀行であり、経営効率が比較的高いです。 |
| 根拠 | 1株当たり1,200円弱という低価格で買える高配当金融株という点で選びました。 |
| 株価 | 1,248円(2025/03/06) |
| 1株あたり配当金 | 22円(2024年3月 実績) |
| 配当利回り | 約4.0%(予想) |
| 詳細 | <https://www.resona-gr.co.jp/> |
(8)ENEOSホールディングス
| 👍株価 | 803.6円 / 1株 | 2025年3月6日 |
| 👍配当金 | 22円 / 1株 | 2024年3月実績 |
| 👍配当利回り | 約 3.3 % | (予想) |
| 👍株価 | 803.6円 / 1株 | 2025年3月6日 |
| 👍配当金 | 22円 / 1株 | 2024年3月実績 |
| 👍配当利回り | 約 3.3 % | (予想) |

ガソリンスタンドでおなじみのENEOSね。
<詳細情報>
| 証券コード | 5020 |
| 企業概要 | 国内石油元売り最大手で、JXエネルギー(旧新日本石油)と東燃ゼネラル石油の統合により誕生しました。 ガソリン・軽油など石油精製販売を中心に、金属(非鉄精錬)、石油・天然ガス開発、化学品など幅広く手掛けます。 ガソリンスタンド「ENEOS」を全国展開し、国内シェアはトップです。旧社名はJXTGホールディングス。 |
| 将来性 | ガソリン需要は徐々に減少傾向ですが、ENEOSは事業多角化や海外資源開発で収益源を確保しています。 |
| リスク要因 | 原油価格や為替の変動で収支が大きく変動します。 |
| 特徴 | 株価水準が低位(約800円)で、手軽に高配当を狙える点が特徴です。 |
| 根拠 | 1株千円未満で国内エネルギー覇者の安定配当を得られるため選びました。 |
| 株価 | 803.6円(2025/03/06) |
| 1株あたり配当金 | 22円(2024年3月 実績) |
| 配当利回り | 約3.3%(予想) |
| 詳細 | <https://www.hd.eneos.co.jp/> |
(9)オリックス
| 👍株価 | 3,149円 / 1株 | 2025年3月6日 |
| 👍配当金 | 98.6円 / 1株 | 2024年3月実績 |
| 👍配当利回り | 約 3.3 % | (予想) |
| 👍株価 | 3,149円 / 1株 | 2025年3月6日 |
| 👍配当金 | 98.6円 / 1株 | 2024年3月実績 |
| 👍配当利回り | 約 3.3 % | (予想) |

リースやレンタカーで有名なオリックス!
<詳細情報>
| 証券コード | 8591 |
| 企業概要 | 総合リース業の最大手であり、保険・銀行・不動産・空港運営・プロ野球(オリックス・バファローズ)など多角的な事業を展開する企業グループです。 元々リース会社として出発しましたが、積極的なM&Aで事業の幅を広げ、今では「事業持株会社」に近い存在です。 近年は資産運用(投資ファンド)や環境エネルギーにも注力しています。 |
| 将来性 | 非常に幅広い収益源を持ち、環境変化に柔軟に対応してきた経緯があります。 |
| リスク要因 | 多角化している分、景気後退時の影響を幅広く受ける可能性があります。 |
| 特徴 | オリックスは「高配当+優待」の二刀流で個人投資家人気が高かったですが、優待廃止後も高配当株として十分魅力があります。事業の多様性から「日本版バークシャー・ハサウェイ」とも呼ばれ、安定感があります。 |
| 根拠 | ビジネスモデルの安定性と着実な株主還元姿勢が選定理由です。 |
| 株価 | 3,149円(2025/03/06) |
| 1株あたり配当金 | 98.6円(2024年3月 実績) |
| 配当利回り | 約3.3%(予想) |
| 詳細 | <https://www.orix.co.jp/grp/> |
(10)SOMPOホールディングス
| 👍株価 | 4,646円 / 1株 | 2025年3月6日 |
| 👍配当金 | 100円 / 1株 | 2024年3月実績 |
| 👍配当利回り | 約 3.0 % | (予想) |
| 👍株価 | 4,646円 / 1株 | 2025年3月6日 |
| 👍配当金 | 100円 / 1株 | 2024年3月実績 |
| 👍配当利回り | 約 3.0 % | (予想) |

保険のSOMPOって名前で聞いたことある!
<詳細情報>
| 証券コード | 8630 |
| 企業概要 | 損害保険大手の一角で、損保ジャパンを中心に生命保険や介護事業、海外保険事業も展開する保険持株会社です。 旧安田火災・日産火災などの流れを汲み、損保では国内シェア2位。グループにSOMPOひまわり生命や介護サービス会社も擁し、総合保険・ヘルスケア企業を目指しています。 |
| 将来性 | 損保事業は自動車保険等で安定収益を上げています。 |
| リスク要因 | 大規模自然災害や予測困難な保険金支払い(パンデミック等)が発生すると業績が急変するリスクがあります。 |
| 特徴 | 損保3社(MS&AD, 東京海上, SOMPO)の中で株価水準が低め(一時4千円割れ)で、購入しやすいです。 |
| 根拠 | 株価が1株5千円以下で、国内有数の保険ブランドの株主になれる点に注目しました。 |
| 株価 | 4,646円(2025/03/06) |
| 1株あたり配当金 | 100円(2024年3月 実績) |
| 配当利回り | 約3.0%(予想) |
| 詳細 | <https://www.sompo-hd.com/> |

高配当銘柄を狙って、資産をしっかり増やしていこう。
5. ミニ株(単元未満株)の始め方と注意点
5.1 取引可能な証券会社の選び方
株式投資を始める際、最初に考えるべき重要なステップの一つは、「どの証券会社で取引を行うか」です。
証券会社の選び方によって、取引のコストや利便性、使いやすさが大きく異なり、特にミニ株(単元未満株)の取引を行う場合には、少額からの投資に対応している証券会社を選ぶことがポイントとなります。
ここでは、株式投資初心者が取引可能な証券会社を選ぶ際に注意すべきポイントや、各証券会社の特徴をわかりやすく解説します。
(1)手数料を比較する
まず、証券会社を選ぶ際に重要なポイントの一つは「手数料」です。
ミニ株(単元未満株)投資では少額取引が多くなるため、手数料の割合が高いと利益を削ることになります。
各証券会社の手数料体系をしっかりと確認しましょう。
例えば、SBI証券の「S株」は、少額取引に対応したミニ株(単元未満株)のサービスで、手数料が他の証券会社と比べて安いのが特徴です。
特に、100株単位の取引ではなく、1株単位で少額から購入できるため、手軽に取引を始めたい初心者には最適です。
さらに、SBI証券では手数料が段階的に設定されており、大量に取引を行う場合でもコストを抑えられます。
詳細は、 SBI証券の公式サイト で確認してください。
一方で、マネックス証券の「ワン株」は、米国株を含めた幅広い銘柄に対応していますが、取引手数料がやや高めです。
ただし、米国株に興味がある初心者には、ワン株の使いやすいツールが提供されており、取引の手間が少なくなります。
詳細は、マネックス証券の公式サイト をご確認ください。

手数料をしっかり比較して、無駄なく投資を進めよう。
(2)取引の利便性を考える
次に、取引の利便性も重要な要素です。証券会社ごとに提供しているツールやサービスは異なり、初心者でも使いやすいかどうかを事前に確認する必要があります。
楽天証券の「かぶミニ」は、楽天ポイントを使って株を購入できるというユニークな特徴があります。
日常生活で貯めたポイントを投資に使えるため、リスクを抑えつつ少額から始めることが可能です。
楽天証券は、初心者でも使いやすい画面設計と豊富な取引ツールを備えているため、投資を始めるには非常に便利なプラットフォームです。
詳しい内容は、楽天証券の公式サイト を参考にしてください。
また、auカブコム証券の「プチ株」は、積立投資にも対応しており、少額からコツコツと投資を続けたい初心者にとって非常に便利です。
定期的に少額ずつ株を購入することで、リスクを分散しながら長期的な資産形成を行うことが可能です。
auカブコム証券では、操作性の高いスマホアプリも提供しているため、いつでもどこでも取引ができる点も魅力です。
詳細については、auカブコム証券の公式サイト をご確認ください。

便利なツールを使って、少額から楽しく投資を始めましょう!
(3)配当金の受け取り方法を確認する
ミニ株(単元未満株)での投資を考える際、配当金の受け取り方法も確認しておきましょう。
配当金は、株を保有している限り定期的に支払われるもので、これをどのように受け取るかは証券会社によって異なります。
多くの証券会社では、株式数比例配分方式という方法で、証券口座に直接配当金が入金されるため、手続きが簡単です。
これにより、配当金を受け取った後にすぐに再投資を行うことが可能で、資産形成を効率的に進めることができます。

配当金の受け取り方を知って、スムーズに投資を進めよう!
5.2 ミニ株(単元未満株)取引におけるコスト比較
各証券会社のミニ株取引にかかるコストは異なります。
SBI証券の「S株」や楽天証券の「かぶミニ」では買付手数料が無料ですが、楽天証券ではリアルタイム取引には0.22%のスプレッドがかかります。
一方、マネックス証券の「ワン株」では、買付は無料ですが売却時に0.55%の手数料がかかります。
auカブコム証券の「プチ株」も、同様に定期買付は無料で、通常の売買手数料が発生するため、少額投資であっても手数料の負担を考慮する必要があります。
これらを踏まえ、取引回数や取引額に応じて最適な証券会社を選ぶことが重要です。

各証券会社の手数料は異なるから、取引前にしっかり確認しておきましょう。賢い選択が、長期的な利益につながりますよ!
SBI証券 👍おすすめポイント!
SBI証券の「S株」は、売買手数料無料!
スプレッド(取引コスト)なし!
○手数料無料のSBI証券がおすすめ。
○口座開設は無料!
\ SBI証券で投資を始めよう! /

SBI証券 👍おすすめポイント!
SBI証券の「S株」は、売買手数料が無料!
スプレッド(取引コスト)なし!
○手数料無料のSBI証券がおすすめ。
○口座開設は無料!
\ SBI証券で投資を始めよう! /

6. まとめ
ミニ株(単元未満株)を活用した配当金投資は、初心者にとって手軽かつ効果的な資産形成手段です。
少額からでも高配当銘柄に投資することで、定期的に配当金を受け取りつつ、リスクを抑えた長期的な資産形成が可能です。
この記事では、SBI証券やマネックス証券、楽天証券などの主要な証券会社のミニ株サービスを比較し、手数料や配当金受取方法の違いを解説しました。
今、投資を始めるなら、少額から始められるミニ株が最適です。

ミニ株で少額投資、配当金を狙うのが賢い選択です。
手数料が実質無料のSBI証券や、楽天ポイントを利用できる楽天証券など、あなたに合った証券会社を選んで口座開設してみましょう。
投資初心者でも安心してスタートできる環境が整っているので、将来の資産をコツコツと積み上げていく一歩を踏み出してください。
今すぐ証券会社で口座を開設して、配当金を狙った投資を始めましょう!

自分に合った証券会社を選んで、安心して投資を始めましょう!
<付録> ミニ株(単元未満株)の基本
ミニ株(単元未満株)とは、通常の株式取引で必要な単元株数(多くの場合100株)よりも少ない株数で取引できる仕組みのことです。
例えば、1株から購入できるため、少額から投資を始めたい方に適しています。
ミニ株(単元未満株)のメリット
- ① 少額から投資可能
- 高額な株式でも、1株から購入できるため、初心者や資金の少ない投資家でも始めやすいです。
- ② 分散投資がしやすい
- 少額で複数の企業の株式を購入できるため、リスク分散がしやすくなります。
- ③ 人気銘柄にも手が届く
- 高額な株価の銘柄でも、ミニ株(単元未満株)なら購入しやすくなります。
- ④ 配当金も受け取れる
- 保有株数に応じて、配当金を受け取ることができます。
- ⑤ 株式投資の学習
- ミニ株(単元未満株)を通じて、株式投資の基本的な仕組みや利益、損失の発生について学ぶことができ、本格的な株式投資に備えることができます。
ミニ株(単元未満株)のデメリット
- ① 売買手数料が高い場合がある
- 証券会社によっては、手数料が高めに設定されている場合があります。
- ② 売買のタイミングが限られる場合がある
- 通常の取引と比べて、希望するタイミングですぐに売買できない可能性があります。
- ③ 希望の価格で取引できない可能性がある
- リアルタイムで取引でない場合、株価が変動している間に希望の価格で約定しない可能性があります。
- ④ 議決権がない
- 通常、1単元未満の株式保有者には議決権が付与されません。
- ⑤ 株主優待を受けられない場合がある
- 企業によっては、株主優待の対象が単元株保有者のみの場合があります。
「ミニ株」について
「ミニ株」は証券会社のサービスで、共通した厳密な定義はないようです。
株式ミニ投資 という、株式を10株単位で購入できる取引方法を ミニ株 と呼ぶこともあるようです。
本サイトで紹介する証券会社は、単元未満株と同じ1株からのミニ株取引を提供しています。
そのため、本サイトでは「ミニ株(単元未満株)」と記述して、ミニ株 と 単元未満株 は同じものとしています。
各証券会社が提供するミニ株(単元未満株)サービスには、SBI証券の「S株」、楽天証券の「かぶミニ」、マネックス証券の「ワン株」、三菱UFJ eスマート証券の「プチ株」などがあります。
ミニ株(単元未満株)は、少額から始められる点で初心者にも取り組みやすい投資方法です。
ただし、手数料や売却時の制限などのデメリットもあるため、十分に理解した上で取引を行うことが重要です。
ミニ株(単元未満株)の取り扱いは証券会社によって異なります。
利用する証券会社の手数料や取扱銘柄数など規定を確認しましょう。

本サイトでは ミニ株 と 単元未満株 は同じものとして扱うね。
ミニ株(単元未満株)の本サイトでの扱いや詳細は以下の記事をご覧下さい。
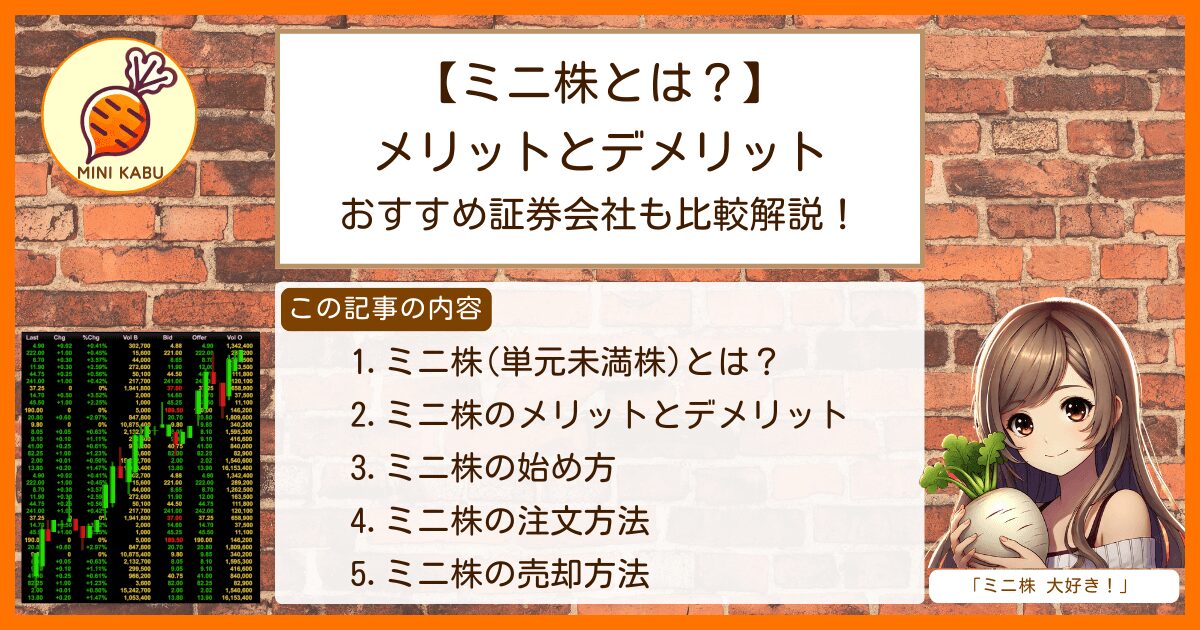 | 【ミニ株(単元未満株)】メリットとデメリット おすすめ証券会社も比較解説! ミニ株(単元未満株)初心者におすすめの株式投資方法を徹底解説!1株単位で取引可能なサービスや少ない資金で始める方法、売買手数料のポイントまでわかりやすくご紹介します。これから投資を始めたい方必見! |

最後まで読んで頂き、ありがとうございました。